司法書士が土地家屋調査士に挑戦するため、独学で測量士補受けてきた
測量士補の試験を受けてきました
タイトルのとおりです。
前の日曜日に測量士補の試験を受けてきまして、自己採点21点/28点でたぶん合格しました。
なぜ、司法書士の私が測量士補の試験をうけたのか、ことの経緯から説明します。
司法書士業務における調査士資格の必要性を感じた
司法書士をやっていると表示登記の相談が多い
田舎で司法書士業務をしておりますと、表示登記に関する相談もかなりの割合でされます。
また、権利登記と関連して、前提として表示登記をする必要があることも多く、そのたび知り合いの土地家屋調査士さんに依頼しておりました。
なかなか、近くに土地家屋調査士さんがいないこともあり、業務が円滑に進まなかったり
また、調査士報酬の単価の高さに魅力を感じ、
もういっそ「自分でやれればいいなぁ」と思うようになり、
この度土地家屋調査士試験をうけることを決意しました。
土地家屋調査士試験、どうやって勉強する?独学?
いざ、試験を受けるとなると、予備校にいくか、独学かの選択を迫られますが、
司法書士試験では1年目予備校にいって、その後は独学したという経験から、
「予備校は勉強の仕方を教えてくれるところであり、合格させてくれるところではない」
ということを確信しております。
司法書士試験の際に、資格試験の勉強の仕方は、頭だけでなく体に覚えこませましたから、独学で挑戦することを決意しました。
土地家屋調査士試験の概要
試験は午前と午後に分かれており、測量士補があると午前は免除される
独学で勉強するとなると、何よりもまず、試験の概要ですが
調査士試験は、午前試験と午後試験に分かれています。
測量士補などの一定の資格を持っていると午前試験が免除されるようで、5月に測量士補を受けて、その年の10月の調査士試験に臨むというのが一般的な受験生がとる戦略のようです。
私も例にならって、測量士補の試験から受験することを決意し、
先週の日曜日に受験してきました。
測量士補の受験について
測量士補の勉強についても、土地家屋調査士試験と同様に独学で挑みました。
勉強に使用したテキスト等
勉強には、「やさしく学ぶ測量士補試験合格テキスト」という本を一冊だけ購入し、試験日までに三周繰り返し勉強しました。
テキストを選んだ理由としては、各章ごとに例題や過去問がついているため、別途過去問集などを買う必要がないと思ったからです。
過去問集を別途買ったとしても、たぶんそこまで勉強時間が取れなかったと思うので、結果的には、受験生なら絶対知っておかなければならない部分を重点的に勉強できたかなと思います。
テキストを裁断し、自炊したものをipadに入れて読んでました
テキストを購入したその日に、カッターナイフで裁断してしまって、スキャンスナップで自炊しました。
新品の本を裁断するのは、やったことない人は結構躊躇するかもしれませんが、私は結構漫画とか自炊してますので、まったく気にしません!!
自炊したテキストは、ipadの「GoodNotes」というアプリを使って勉強しました。
この「GoodNotes」というアプリは、アップルペンシルと相性がよくて、必要なことを書きこんだりするのがとても便利です。
勉強を本格的に始めたのは3週間前
勉強を早めに始めないとと思っていても、なかなか手を付けられず、ゴールデンウィーク明けにやって本格的に勉強を開始することができました。
ipadにテキストを入れていたおかげで、持ち歩くのが便利で、病院の待ち時間等スキマ時間を有効活用して勉強しました。
それで平日は、2、3時間は、土日は5、6時間は勉強できました。
わからないところがあっても、とりあえず一周してしまうことが重要
資格試験の勉強では、よくわからない問題に出くわすことがあります。
そんな時、その問題をわかるまで勉強するよりも、とりあえずとばしてしまった方が良かったりします。
資格試験に落ちる人の特徴として、試験勉強の際に一つ一つの問題にこだわり過ぎているような気がします。
一つ一つの問題を丁寧に勉強しすぎて、試験の全範囲をカバーできずに試験に臨んで落ちたなんてなると本末転倒です。
それから試験範囲を一周してみて、そのあとにわからなかった問題に手をつけると意外と簡単に解けたりすることもあります。
繰り返しますが、とりあえず試験範囲を一周こなすことが資格試験の合格の前提条件です。
測量士補試験の難易度は?
測量士補試験の難易度は、ネット上では簡単と書かれていることがよくありますが、実際受験してみて、
問題自体は、そこまで簡単ではない と感じました。
ですので、しっかり事前に勉強していなかったら、落ちることはあると思います。
司法書士が測量士補試験を独学したまとめ
以上、司法書士である私が、測量士補試験に挑戦してみた経験でした。
三角関数は司法書士をやっている人にとっては、高校以来だったり、場合によっては人生ではじめて
これから、受験される方は参考にしてください。


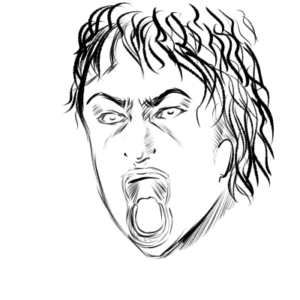
最近のコメント