相続登記の際に参考になる本
相続登記
司法書士にとっては、かなり基本的に登記ではありますが、
実務経験のない人にとっては、意外と難しく感じるのではないでしょうか。
相続登記~何から聞き取るか
さて、相続登記のポイントですが
まず、依頼者から聞き取りを行い、
①被相続人が誰なのか
②相続人が誰なのか
③遺産として何があるのか
④遺産分割の方法および相続人間での合意あるか
このあたりは、最初に聞き取らなければなりません。
そして、これを聞いたうえで、大まかな登記の方針を決め、
必要書類を収集していくというのが
一般的な司法書士の相続登記の進め方ではないでしょうか。
戸籍の読み取り、書類の作成方法について
司法書士実務経験がない人でおそらく
①戸籍の見方
②それに基づく相続人の確定
③相続人確定後、民法上問題がなく、登記的にも問題ない分割協議書の作成
④相続関係説明図の作り方
このあたりの書類の作り方はほぼわからないと思います。
なぜなら、これは試験では全くでないから。
でも心配ご無用です。
これらの事項について、逐一解説された書籍があります。
それは、日本加除出版の
「全訂第2版 相続における戸籍の見方と登記手続」
という本です。
値段は1万5千円ほどしますが、
値段相応の内容があります。
まず、
相続についての一般的な知識だけでなく
戸籍の見本であったり、戸籍から相続人を判断する上での注意点
そして、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成方法まで
すべて記載されています。
相続登記の際に書類の作り方で迷ったときは
基本的にこの本の通りに作って申請すれば基本的に
補正にならない。。。。。。ハズです。
申請支援ソフト(サ〇ポロなど)を入れてるからいいやって
人もいるかもしれませんが
申請支援ソフトの特に相関図はかなりアバウトに作られているため
自動作成された書類をそのまま法務局に出すと
場合によっては補正もしくは取り下げになるかもしれません。
あと、あまり変な書類を作ると恥かくので注意が必要です。
また、相続人がだれかという点は
あまりお客さんが言ってることはあてにならないので、
お客さんの話は一つの情報として
相続人の判定にあたっては、必ず戸籍をもとに判断するように
した方がいいと僕は思います。
(戸籍も相続関係の証する一資料であることには変わりありませんが)
最後に
相続登記は、合格直後の新人にとってはわからないことも多いと思います。しかし、司法書士にとっては基本的な登記であり、お客さんもできて当然と思っていますので、確実に理解し依頼に対応できるようにしましょう。
もし興味があれば、専門書が置いてある大きめの本屋なら本ページで紹介した本も置いていますので、手に取って見てみてください。

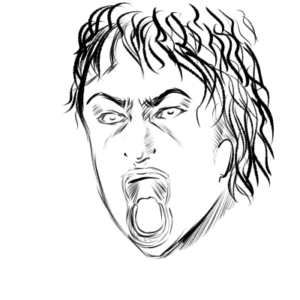
最近のコメント